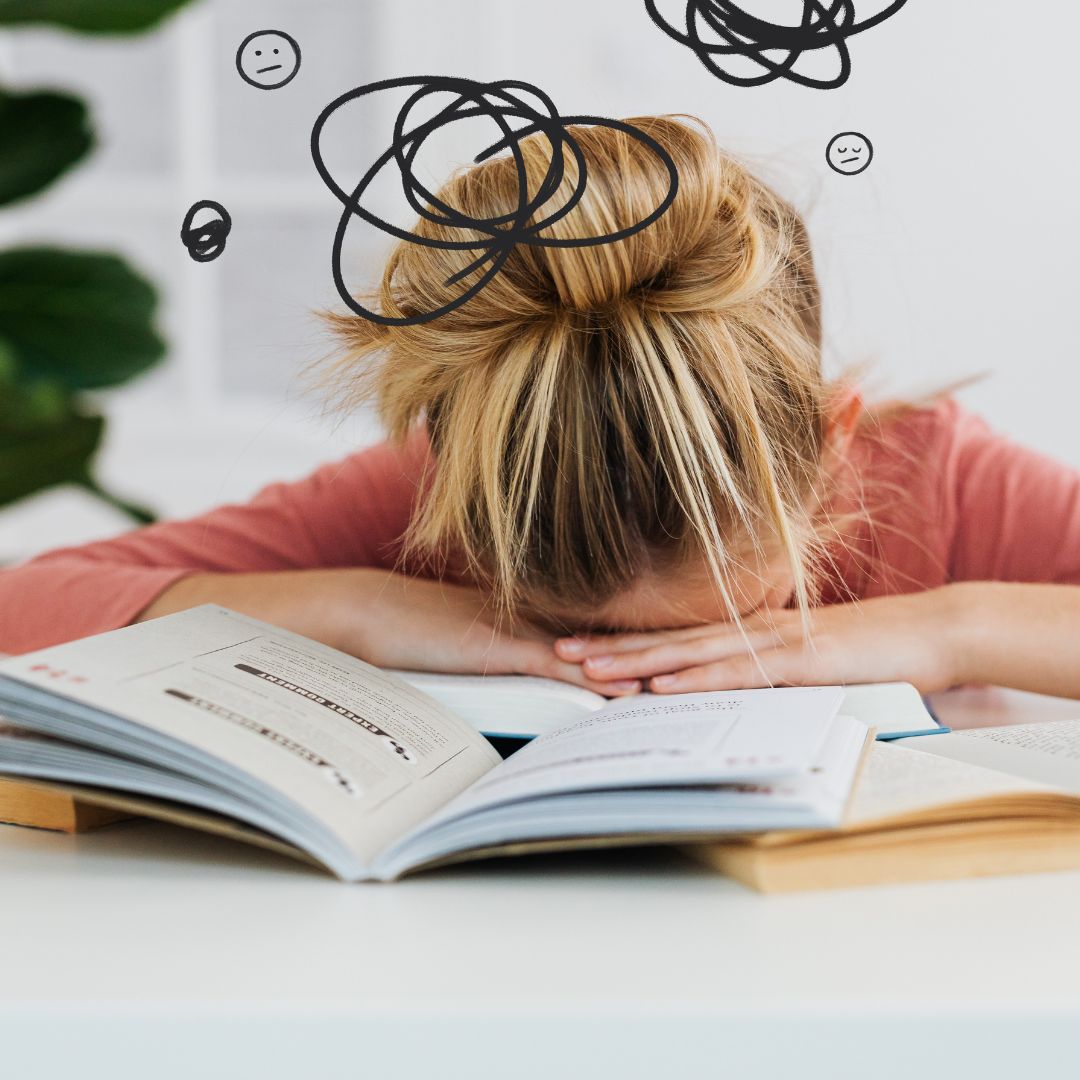実は誰でもなりうる?介護職に多い「隠れ職業病」とは
「介護職」と聞いて、どんなイメージを思い浮かべますか?
「重労働」「肉体的にキツい」といった身体的な負担を想像する方が多いかもしれません。しかし、介護の現場には、目に見えにくい、精神的な負担が原因で起こる「隠れ職業病」が潜んでいます。そして、その症状は、介護職ではない私たちにとっても決して無縁ではありません。
今回は、介護職に多い**メンタルヘルスに関わる3つの「隠れ職業病」**を紹介します。
1. 感情労働による「燃え尽き症候群(バーンアウト)」
介護は、利用者さんの心に寄り添い、感情を深く理解することが求められる仕事です。常に高い共感性や優しさを求められるため、自分の感情を抑えたり、相手の感情に引きずられたりすることが多くなります。
このような**「感情労働」が過度になると、心身ともにエネルギーが枯渇し、ある日突然、糸が切れたように無気力になってしまいます。これが「燃え尽き症候群(バーンアウト)」**です。仕事への情熱を失い、深い疲労感や達成感の欠如を感じるようになります。
これは、顧客対応をする営業職や、人の悩みを聞くカウンセラーなど、多くの職種で起こりうる症状です。
2. 人間関係のストレスによる「適応障害」
介護の現場では、利用者さんやそのご家族、そして同僚との密なコミュニケーションが不可欠です。しかし、価値観の相違や誤解、職場の人間関係のトラブルなど、複雑な人間関係からくるストレスは避けられません。
このストレスが限界を超えると、気分が落ち込んだり、不安感が強くなったりして、日常生活に支障をきたす**「適応障害」**を発症することがあります。
これは、部署異動や転職、人間関係のトラブルなど、環境の変化に適応しようとする誰もが経験する可能性があるものです。
3. 責任感の重圧による「介護うつ」
介護職は、人の命を預かる、非常に責任の重い仕事です。些細なミスが、利用者さんの命に関わる重大な事故につながる可能性もあります。このプレッシャーは、常に介護士の心に重くのしかかっています。
「自分がしっかりしなければ」「もっと頑張らなければ」という強い責任感は、自分を追い詰める原因となります。その結果、気分の落ち込みや不眠、食欲不振といった**「うつ病」**の症状が現れることがあります。
これは、プロジェクトの責任者や医療従事者など、重大な責任を伴う仕事に就いている人だけでなく、子育てや家族の介護を担う人にも見られる症状です。
あなたは大丈夫?「隠れ職業病」から身を守るために
これらの「隠れ職業病」は、特別な人がかかる病気ではありません。真面目で責任感が強い人ほど、そして、周りに助けを求めるのが苦手な人ほど陥りやすい傾向にあります。
もし、あなたが次のような兆候を感じたら、心身からのSOSかもしれません。
- 朝起きるのがつらい
- 仕事に行くのが憂鬱
- 何をしていても楽しくない
- なぜかイライラする
- 食欲がない、または食べすぎてしまう
- 眠れない、または寝すぎてしまう
これらの症状が続くようであれば、信頼できる人に相談する、趣味の時間を作る、休暇を取ってリフレッシュするなど、心にゆとりを与える時間を意識的に作ることが大切です。
介護職でなくても、私たちの誰もが、いつの間にか「隠れ職業病」の渦中にいるかもしれません。自分の心の声に耳を傾け、無理をしない働き方、生き方を模索するきっかけになれば幸いです。